7-A 他のグラフとの関連を見る
|
|
a 複数のグラフの処理
b 比較して推論する
c 比べて始めて分かること
|
 複数のグラフの処理 複数のグラフの処理
|
|
●先週くわしく説明してもらったおかげで、だいぶグラフ問題のアプローチが分かってきました。
1 情報の中から大事なものを選び出して、文章の形に変換する
2 歴史や経済など、何か理論的枠組みを使ってグラフの動きを説明する。
こんなところでいいでしょうか?
■そのとおり。
|
 |
●でもこの間もっと衝撃的な問題を見ちゃったんです。わーお、あまりにも恐ろしくて私言えない!
■グラフがいくつも並んでいて、どこからどう手を付けてよいか分からない…
●あれ、どうして分かっちゃうんですか。
複数グラフは典型的問題
■それはすごく典型的な問題だからだよ。この頃は、グラフが一つだけなんて問題の方が珍しいんだ。
●なーんだ、そーだったのか、なんて感心している場合ではありませんね。見たとたん、一瞬凍り付いちゃいました。一難去ってまた一難。私はいったいどうすればいいのー?
|
| 全部のグラフを利用する |
■グラフが複数ある場合は、互いに比較してモデルを立てるというやり方をとる。いくつかのグラフを結びつける一つのモデルをつくるんだ。
●モデル?
■それぞれの要因がどう関係して、結果につながっているか、という仕組みを考えるんだ。
●なるほど。複数の原因か。
■グラフかいくつかあるということは、原因は一つじゃないことが多いね。
●でも、そしたら全部のグラフに触れなければいけないんですか?
■そうだよ、出題者としては、全部の資料を十分に利用して論を組み立てているかどうかを見る。一つのグラフからは言えることに限りがある。いくつかのグラフを参照して、総合判断をすることが求められるんだ。さっそく具体的な問題を見てみよう。
|
 |
●おーおー、いきなり四つのグラフですか。
■最初が円グラフだ。ここから分かることは何だろう?
●CO2排出量の大きいところは、アメリカ、中国、ロシア、日本、インドという順番だということです。
■アメリカはやっぱり世界一のCO2排出国だね。
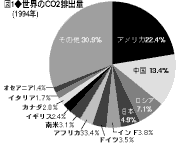 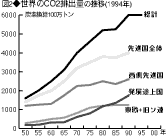
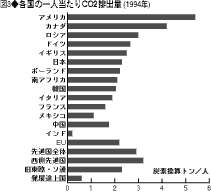
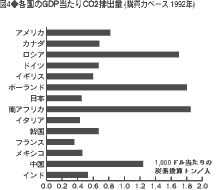
●でも日本もけっこうCO2排出量が多いなあ、もっと政府が規制を強化しなきゃダメですね。だいたい日本の政府はいつも対応が遅くって…
■そんな単純な結論でいいのかな? 日本が多いと言うけど、円グラフを見ると、中国、ロシアはもっと多いよ。
|
| 客観的に検討する |
●ありゃりゃ、本当ですね。日本だけが悪いのではないな。ロシア・中国も悪い! インドもおまけによくなーい! ついでに世界全部よくなーい!
■待て待て。主観的によい悪いの判断をする前に、もう少しグラフの中味を客観的に検討しよう。何で中国とロシア、インドは排出量が多いのかな?
|
 比較して推論する 比較して推論する
|
|
■図3(各国の一人当たりCO2排出量)を見る限り、図1でCO2排出量が多かった中国やインドは、一人当たり排出量ではずっと下だね。どうしてだろう?
●CO2は、いっぱいエネルギーを使うと多く排出されるって、新聞に書いてました。大量生産・大量消費の生活が原因だって。
■でも、これらの国はまだ経済発展が十分でなくて、大量消費社会にはなっていない。その考えでは説明できないね。でも中国・インドも全体量としてはたくさん出している。この原因は?
|
|
人口とC02の関係は?
|
●人口が多いから、かな? ちりも積もれば山となる。
■そう。人口が多いから国全体として排出量が多くなってしまう。つまり第1 図と第3 図を比べると、CO2の問題は生活スタイルの問題であると同時に人口問題でもあることが分かる。
●なるほど、たしかに複数のグラフを見比べると、発見がありますね。
グラフのデータから推論する
■上右のグラフを見てみよう。西側先進国全体の排出量が1970年代半ばから横這い状態なのが、分かるかい?
●ええ。多少の増減はありますけど、あまり変わっていませんね。それに対して発展途上国の排出量は一貫してのびている。
■なぜ先進国では横這い状態になっているのだろう?
|
| 先進国の努力?
|
●努力したんですか? まさかね。
■いやその「まさか」なんだよ。1973年のオイル・ショックの後、先進国は競って省エネルギー、つまりエネルギーの節約に努めたんだ。火力発電などを減らし、原子力発電にシフトしている。原発はCO2排出が少ないんだ。
●原発にもいいことがあるんですね。
■危険もあるけどね、とりあえずCO2に関してはいいみたいね。
●先進国もそれなりに対策している…と。
|
 比べて始めて分かること 比べて始めて分かること
|
| 温暖化の原因は途上国? |
■政府の悪口ばっかり言っても問題は解決しないんだ。逆に発展途上国の排出量はどうなっている?
●1970年代半ばからだと二倍以上に増えています。CO2による温暖化が問題になったのが最近だったことを考えれば、CO2排出の問題は、主に途上国の急速な経済発展が原因かな…えー、まさか? 温暖化問題の原因は先進国の大量消費社会、とくにアメリカにあるって新聞で読みましたけど!?
■だけどグラフを見る限り、結論は逆だね。先進国は70年代からあまり変化せず、途上国が急激に増えている。つまり最近10〜20年間でCO2が問題になった一つの原因として、途上国の経済発展が重要なんだ。
もちろんアメリカは一人あたりの排出量も多いし、人口も多い。しかも京都議定書を無視している。大きな責任があるのは明らかだけど、CO2の問題はそれだけではないんだね。
データから常識を修正する
●少なくとも先進国の責任だ、と決めつければすむ話ではないみたい。
|
| 決まり切った環境対策の主張はダメ |
■よく環境問題というと、消費生活を変えろとかもっとリサイクルをせよ、という決まり切った主張をすればよいと思っている人がいる。それは間違いではないけれど、でもこの資料から考える限り、途上国のCO2規制の問題も大きいことが分かる。
●「自分たちの生活を変えよう」と書くと全然間違いなんですか?
■少なくとも途上国問題に触れないで、そういう主張をしたら不公平かもしれないね。
●ショックだなー。必殺解答パターンを覚えただけでは十分じゃないのかー。
図4から分かることは?
■ところで中国のGDP あたりの排出量は下右 図を見ると、かなり多いよね。これは何を意味しているのだろう?
●他に多いのは、ポーランド、南アフリカ、ロシアですね。ヨーロッパや日本は意外に少ない。でも「GDP あたりの排出量」って意味が分からない…
|
| GDPあたり排出量は、環境対策の進行を表す |
■GDPは、国内の経済活動の水準を表す。つまり、同じ価値たとえば1000ドルの生産物を作るにあたって、どのくらいCO2が排出されたか、を表す。難しい言い方をすると、経済活動一単位あたりのCO2排出量だね。
経済活動すると、どうしてもCO2が排出される。でも、この値は環境対策を進めることで、小さくすることができる。これが大きい国は、対策や技術が遅れていることになるね。
●たぶん、これらの国の政府が経済活動に一生懸命で、環境対策まで手が回らないのかもしれませんね。
■ある程度経済が発達していないと、環境対策にはなかなか手が回らないものだよ。古いことを言うようだけど、日本だって高度成長以前は、川の水質とかひどかったんだよ。隅田川なんて夏になるといやなにおいがしたり、ゴミがいっぱい浮いていたり、魚がいなくなったり…少しきれいになったのが、70年代以降だね。
●へー、そうだったんですか? 知らなかったー。昔は自然がきれいだったというのは、幻想なんですね。
|
|
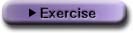 |
All text and images (c) 2001 VOCABOW. All rights reserved. |