2009年4月6日 ●こんにちは。専務です2
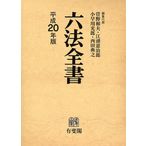
こんにちは。遅刻魔の「専務」です。遅刻=重役出勤ということで専務というアダナを付けられました。でも、今は、ホトンド遅刻していないんですよ。どちらかというと朝早めに学校の自習室に行って勉強しているぐらい。入学したばかりの頃は、朝学校で勉強している人の話を聞くと「なんて勤勉なんだ!」と感動したけど、まさか自分もそうなるとは思いませんでした。「怠惰な生活からの脱出」も法科大学院に入った非公式目的のひとつだったので、その点では、大進歩を遂げていると、自分で自分をほめています。
ただ、ほかの人はもっと勤勉なんですよ!たとえば、エレベーターの中で聞いた、デキそうな2人組の会話。「ナポレオンって睡眠4時間が普通で、5時間だと怠惰、3時間だと勤勉なんだって」「そうか〜。じゃ、俺は普通なのか」「私も」「まだダメだね」との会話が…。それって、この2人組は、毎日睡眠4時間で頑張ってるってことですよね?私はテスト前でも睡眠6時間は確保していたので、かなり申し訳ない気分になりました。ホント、ロースクールの学生って、エライと思います。
ところで、(私が担当して)1回目のコラムではロースクールの授業が「法律を知っている前提」で進められていることに驚いたと書きましたが、私の場合、超〜初心者なので、日常用語と法律用語の違いにも驚きました。
例えば「悪意」。悪意って言ったら、悪い意思、悪い心を持っていること、人を陥れようとする気持ち…ですよね?でも、法律上の「悪意」は、「知っている」っていう意味なんですよ。なんだか、気持ち悪くありませんか?ちなみに、「善意の第三者」っていったら、どういう人だと思います?日常用語だったら、お財布を拾って警察に届けてくれたいい人が「善意の第三者」ってイメージですよね?ところが法律だと「事情を知らない人」って意味になるんですよ。悪い人だって事情を知らなければ「善意」。これって、一般的な感覚からすると、なんだか変ですよね。
このほかにも、「業務上」は、仕事上という意味ではなく「反復する行為の際に」という意味だし、「果実」はフルーツじゃなくて「利益」のこと。アパートの家賃は「果実」なんですよ。法律的には。でも日常用語的には、すごく気持ち悪いですよね!
こんな感じで、ず〜っと法律用語と日常用語の切り替えがうまくできず、混乱しっぱなしでした。授業中も法律用語辞典を引いてばっかりで大事なことが頭に入っていなかった気がします。でも、せっかく他業界から来たのだからこの感覚を失わない方が市民に近い弁護士になれるのかなと最近は前向きに考えています。では、また次回。あ、次回は、1日のタイムスケジュールや予習復習について書く予定です。
参考:私が混乱した「善意」と「悪意」について
繰り返しになりますが、善意とは知らないことをいい、悪意とは知っていることをいいます。道徳的なものではありません。
この「善意」「悪意」という言葉が六法全書にはよく出てきます。たとえば、民法97条3項には「詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗することができない」とあります。これは、例えば、詐欺で家宝の壺を手放してしまった時、民法96条1項で取り消す…つまり、壺を取り戻すことができます。しかし、その詐欺師が、壺を善意の(事情を知らない)第三者に売ってしまった場合、この「取り消し」はできないので壺は取り戻せません。
また、法律行為の発生を決める上で、善意・悪意がキーとなることもよくあります。例えば、民法177条は、不動産は登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。これは、二重譲渡の場合によく問題となります。二重譲渡とは、Aさんが家を売るとき、BさんにもCさんにも売ってしまったような場合です。たとえBさんが先に家を買ったとしても、Bさんに登記がなく、Cさんに登記があれば、この家はCさんのものになります。このルールを定めたものが民法177条なんです。Cさんが悪意だった(家がBさんにも売られていることを知っていた)としてもCさんのものとなります。ただし、Cさんが背信的悪意者(Bさんを困らせるためにわざと家を買った場合など)は、民法177条の「第三者」には含まれず、保護されないことになっています。
善意=知らない、悪意=知っている、この意味さえ把握していれば六法も読みやすくなりますね。あ、でも民法770条1項2号や814条1項1号の「悪意で遺棄」の「悪意」は、「他人を害する意思」という意味…つまり道徳的な悪意を表しています。もう〜法律用語、どちらかに統一してよ!と文句を言いたくなってしまいますね。