2008年12月21日 ●ロー入学までに何をするか
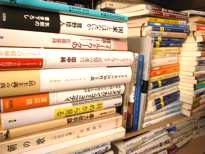
あっという間に時は過ぎ、気づくともう師走。今年も暮れようとしています。世間はジェットコースターのように目まぐるしく変動してますが、ロー生はタフにサバイバルしてます。
そろそろ、4月からの法科大学院進学が決まった純粋未修生の方もいることでしょう。あと3カ月ほどしかありませんが、それまでに何をしたらいいか、この時期よく聞かれます。課題図書を指定してきたり、事前の導入講義を設ける法科大学院もあるようです。社会人の方は、おそらくこれから3月いっぱいまで、めいっぱい働き続けることになり、現実にはあまり学習の時間もとれないことと思います。法律の基本書や判例に馴染むことも必要ですし、新司法試験の設問スタイルがどんなものか研究することも必要ですが、それは、4月から嫌でもやらなければなりません。
今回は、ロースクール入学後に(来年度の法科大学院受験を目指す方の小論文の勉強にも)役立つ「憲法の勉強」の仕方をあげておきます。細かい学説や条文解釈は、いわゆる憲法の基本書や予備校本に載っていますが、日本の政治・経済の仕組み、各国の政治体制との比較、歴史的背景(世界史・日本史)、民主主義の在り方などを体系的に把握する機会は、法科大学院入学後はありませんし、憲法の教科書も、現在の状況は当然追い切れていません。ページ数の関係から、直接法律と関係ない事項は、割愛されています。
「デモクラシーとは?」「憲法って何のためにあるのか?」「国民主権って何なのか?」「なぜ選挙が必要なのか?」「人権とは?」「平等とは?」など直球の質問に、的確に答えることは、実はたいへん難しいのです。なぜならここでは、法律知識というより、むしろ、「現代社会に対する視点」を自分で設定できるかが重要で、目的や制度、立法趣旨の理解、歴史的な時系列の流れ、が問われているからです。しかし、ここの幹について自分なりに整理できていると、実は、法律で問われている問題(法科大学院の定期試験問題でも)でいき詰ったときに、いったん自分の原点に戻ることができます。そうした類の新書は、たくさんでていますので、自分の気に入ったものをいくつか読んでみるのがいいでしょう。ちなみに自分は、中学生向け(たぶん)の「岩波ジュニア新書」からはいりました。
ただし、法科大学院入学後は、教科書の購入などで出費がかさみますので、なるべく図書館を利用しましょう。ちなみに東京都の場合、自分の住所や勤務地以外の区立図書館でも貸出カードを作成できますので、いくつかの区に隣接していると、10冊×2〜3か所の図書館分で20〜30冊は借りることができます。また、いわゆる読んでおくべき古典(例:岩波新書「日本人の法意識」川島武宜)であれば、古本屋で廉価販売されていることもあるので、掘出し物にあえるかも。たまには、神保町界隈を散歩がてら、名著を探索するのもおつなものです。時間があれば、ボカボにもふらっと顔だしてみてはいかが。
by librarian
▼Homeに戻る